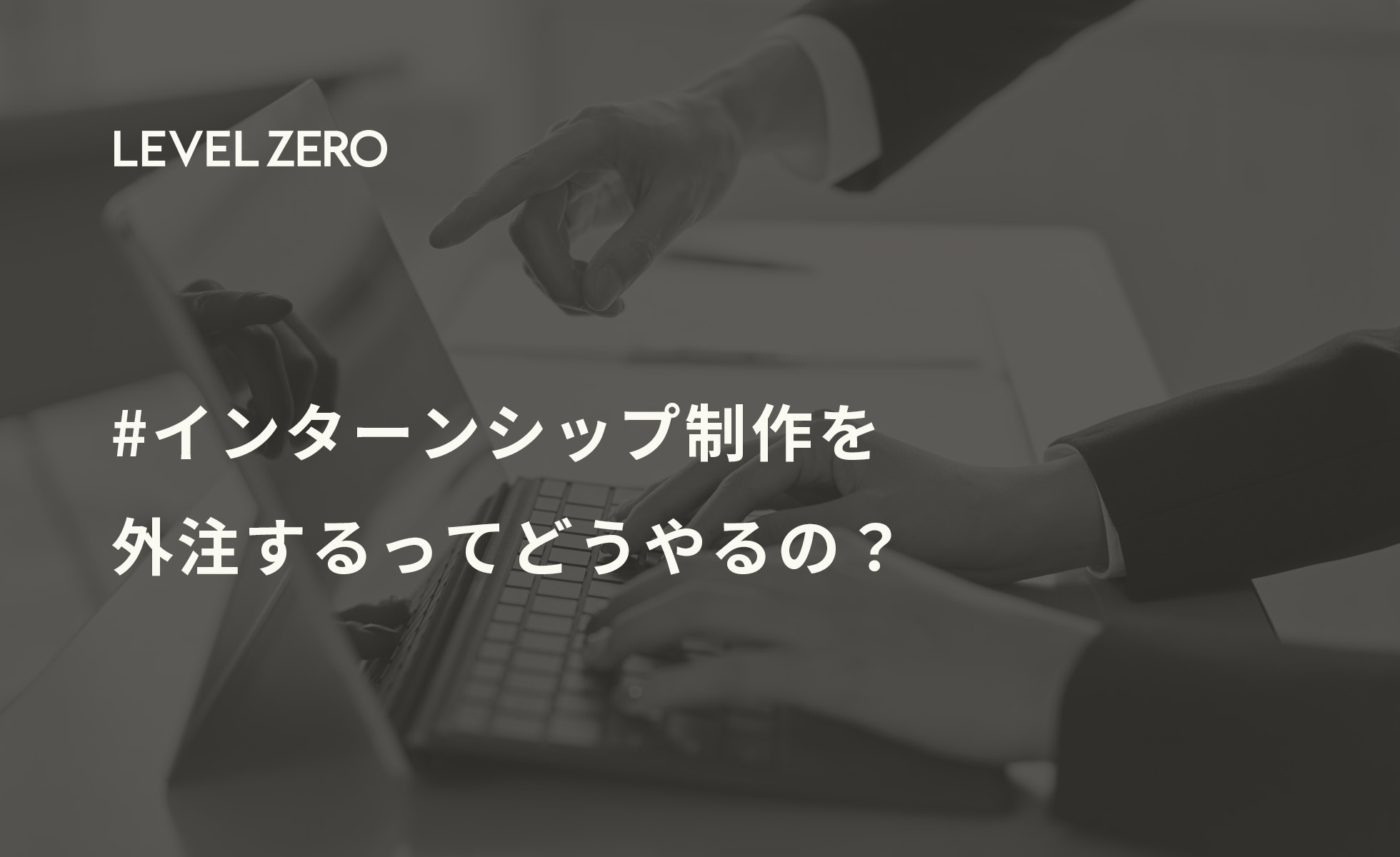
1.はじめに

インターンシップは、企業と学生の接点を作る重要な採用施策のひとつです。しかし、企業内でインターンプログラムをゼロから設計し、運営するのは多くの工数がかかるため、外部に委託(外注)するケースも増えています。では、インターンシップ制作を外注する際、どのような手順を踏めばよいのでしょうか?本記事では、外注のメリット・デメリットや、依頼時のポイントについて解説します。
2.インターンシップを外注するメリット・デメリット
2-1.外注のメリット
プロのノウハウを活用できる
採用戦略やワークショップ設計の専門家によるインターンシップ設計が可能。
工数削減につながる
企業内で一から企画・運営する負担を軽減できる。
学生目線での魅力を引き出せる
外部の視点が入ることで、ターゲット学生に刺さる内容になりやすい。
最新のトレンドを取り入れやすい
外部パートナーは、他社の事例やトレンドを熟知しているため、より効果的なプログラムを設計できる。
2-2.外注のデメリット
コストがかかる
社内で完結する場合に比べ、制作費・運営費が発生する。
自社の文化が伝わりにくい
外部に依頼すると、企業独自の文化や雰囲気を十分に伝えにくくなる可能性がある。
パートナー選びに時間がかかる
適切な外注先を見極めるのにリサーチが必要。
3.インターンシップ制作を外注する流れ

3-1.目的を明確にする
外注する前に、まずインターンシップの目的を整理することが重要です。
- 採用直結型?ブランディング型?
- 内定につなげる目的か、企業認知度向上が主目的か。
- 実務体験型?ワークショップ型?
- 実際の業務に触れてもらうのか、課題解決型にするのか。
- オンライン?対面?ハイブリッド?
- 開催方法によって、必要な準備が変わる。
これらを明確にしないと、外注先との認識ズレが生じやすくなります。
3-2. 外注先の選定
外注先には、大きく分けて以下の3種類があります。
外注先の種類
特徴
向いている企業
採用支援会社
新卒採用に特化したプログラムを提供
インターンと採用を直結させたい企業
イベント運営会社
体験型の企画・運営に強み
企業ブランディングを強化したい企業
コンサルティング会社
組織設計や戦略策定が得意
採用全体を見直したい企業
選ぶ際のポイント:
- 過去の実績(どんな企業のインターンを手掛けたか?)
- 得意分野(技術系インターンに強いか?ビジネス系に強いか?)
- カスタマイズ性(自社の要望に柔軟に対応できるか?)
3-3.企画のすり合わせ
外注先を選定したら、以下の項目についてすり合わせを行います。
✔ 対象学生・採用ターゲット(学年、専攻、スキルレベル)
✔ プログラムの構成(1day / 5days / 長期など)
✔ インターンで評価したいポイント(チームワーク力、論理的思考力など)
✔ 実施方法(オンライン・オフライン)
✔ 運営体制(外部と社内の役割分担)
しっかりすり合わせを行うことで、「思っていたものと違った…」というトラブルを防ぐことができます。
3-4. 実施と運営
運営時には、以下の点に注意するとスムーズです。
事前告知・集客サポート
ターゲット学生にリーチできるよう、SNSや採用サイト、大学との連携を活用。
当日の運営フローの整理
タイムテーブルやトラブル時の対応フローを明確にしておく。
社員の関わり方を明確にする
「誰がどのタイミングで学生と関わるか?」を設計すると、効果的なインターンになる。
3-5.フィードバックと改善
インターン実施後は、学生・社員双方のフィードバックをもとに改善を行います。
- 学生の満足度調査(アンケートや座談会を実施)
- 採用貢献度の分析(本選考のエントリー率、内定承諾率の変化)
- 次回に向けた改善点の洗い出し
外注先と一緒に振り返りを行い、より良いインターンプログラムへとブラッシュアップしていきましょう。
4.外注する際の注意点

4-1.丸投げはNG
外注するからといって、すべてを任せるのはリスクがあります。
自社の採用方針や企業文化を伝えながら、密に連携を取ることが重要です。
4-2.コストの妥当性をチェック
外注費用は、1dayインターンで百万円~、長期インターンなら数百万円規模になることも。
相場をリサーチし、適切な費用であるかを判断しましょう。
4-3.法的リスクの確認
インターンシップは、労働法や雇用関係の問題に関わるケースもあります。特に長期インターンの場合、報酬の有無や労働時間の管理が適切に行われているか確認が必要です。
5.まとめ
インターンシップ制作を外注することで、工数削減やプログラムの質向上につながる一方で、企業の意向をしっかり反映させることが成功の鍵となります。
「目的を明確にし、最適な外注先を選定」
「企画段階でしっかりすり合わせを行う」
「実施後のフィードバックを活用し、継続的に改善」
こうしたプロセスを意識することで、自社に合った最適なインターンシップを構築できるでしょう。
外注をうまく活用しながら、効果的なインターンシップ運営を目指していきましょう!
〈 レベルゼロ インターンシップ事例〉
https://levelzero.co.jp/work_tools/internship-production/