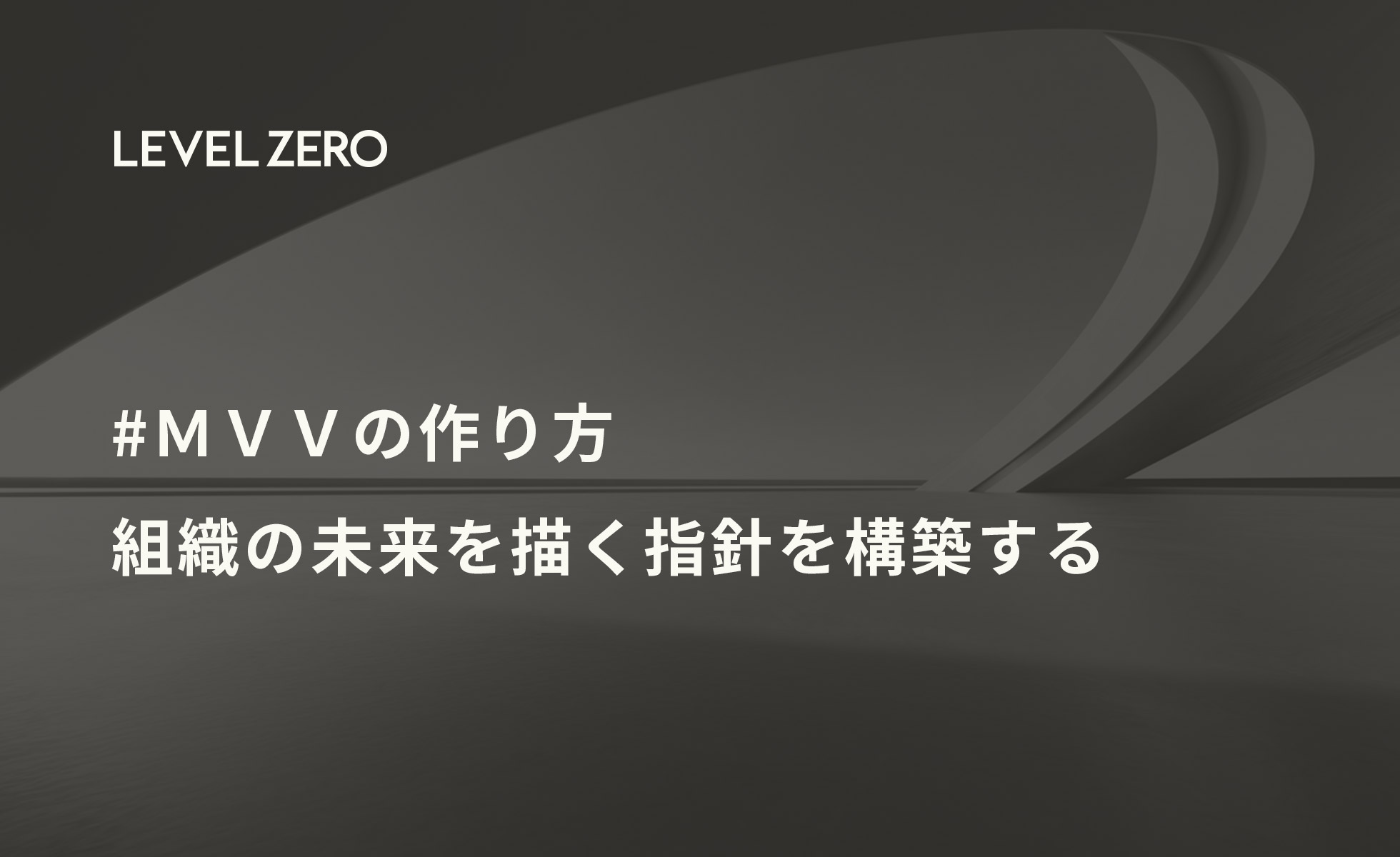
1.MVVとは?
MVVは、「Mission(使命)、 Vision(ビジョン)、 Values(価値観)」の頭文字をとった略語です。
企業や組織が
・「なぜ存在するのか(ミッション)」
・「将来どのような姿を目指すのか(ビジョン)」
・「日常的にどのような価値観に基づいて行動するのか(バリュー)」
を定義し企業のあり方を表現しているのがMVVです。
これらの要素は、組織のアイデンティティや方向性を確立し、全社員が共通の目標に向かって協力するための基盤となります。また、ミッションをかなえるためのビジョン、そのためのバリューといったようにそれぞれ密接に関係しあっています。
2.なぜMVVが必要なのか?
現代社会において、企業は従来のビジネスモデルから進化し、より社会的な責任を果たすことが求められるようになっています。消費者は単なる商品やサービスを購入するのではなく、その背後にある企業の姿勢や価値観に共感し、応援したいと考えるようになっています。
たとえば、環境問題に対する意識の高まりや、社会的公正に対する関心が増加する中で、企業はこれらのテーマに真剣に取り組むことが期待されています。このような背景から、企業が明確なMVVを持つことが、社員のみならず消費者にとっても、ますます重要になっています。
MVVは、企業内においては社内共通の目標や指針として機能し、社員のモチベーション・企業への忠誠心の向上にも寄与します。
他にも、MVVによって企業のあり方を定義しておくと企業と人材のミスマッチを防ぐこともできます。
3.さらに詳しく! MVVの各項目の詳細
3-1.MISSIONとは
ミッション(MISSION)は、企業が「何のために存在するのか」、つまり「存在理由」を明確にするための指針です。これは企業が提供する商品やサービスが社会に対してどのような価値をもたらすか、そして企業が追求するべき主要な目標は何かを示します。
良いミッションは、短く、明確でありながら、企業の本質を的確に捉えている必要があります。たとえば、テクノロジー企業のミッションとして「全ての人々に情報へのアクセスを提供する」といったシンプルかつ強力な表現が考えられます。ミッションが明確であれば、社員は日常業務の中で何を重視すべきかが理解しやすくなり、企業としての一貫性も保たれます。
3-2.VISIONとは
ビジョン(VISION)は、企業が「将来どのような姿を目指すのか」を描いたもので、長期的な目標や夢を示します。ビジョンは、企業が成し遂げたい未来像を具体化するものであり、組織全体が目指すべき方向性を指し示します。
例えば、ある製造業者が「持続可能な社会を実現するために、革新的な製品を提供する世界的リーダーになる」というビジョンを掲げたとします。このビジョンは、企業がどのような成長を遂げたいか、どのように業界でのポジションを確立したいかを示し、社員のモチベーションを高める役割を果たします。
ビジョンが強力であるほど、社員はその目標に向かって努力し、困難な時期でも団結して乗り越えることができます。また、ビジョンは外部に対しても、企業が何を目指しているのかを明確に伝える重要なメッセージとなります。
3-3.VALUEとは
バリュー(VALUE)は、企業が日常的に「どのような価値観に基づいて行動するか」を示すものです。これらの価値観は、社員の意思決定や行動の指針となり、企業文化を形成する基盤となります。バリューがしっかりと定義されている企業は、社員が共通の価値観に基づいて行動することで、社内外からの信頼を得やすくなります。
たとえば、ある企業が「誠実さ、革新、顧客第一」をバリューとして掲げた場合、社員はこれらの価値観に基づいて日々の業務に取り組むことが期待されます。バリューはまた、企業がどのようなリーダーシップスタイルを持ち、どのような企業文化を築いていきたいかを示すものでもあります。
4.MVVを作るプロセス
MVVを作成するプロセスには大きくふたつ、ボトムアップとトップダウンでの決定があります。理想としては両者を組み合わせることが挙げられます。
1.トップダウンアプローチ
トップダウンアプローチでは、経営陣やリーダーシップ層が主導し、組織のミッション、ビジョン、価値観を定義して、それを組織全体に伝え、浸透させていくプロセスです。この方法は、明確なリーダーシップと方向性を示すのに効果的です。
- プロセス
- 経営層が方向性を設定: 経営陣が企業の目的(パーパス)や、どのような社会的貢献を目指すかを深く考え、それに基づいてミッションを定義します。
- ビジョンを描く: 長期的なゴールや組織がどのような未来を築きたいかを経営陣が決定します。
- 価値観を策定: 経営層が組織の文化や行動基準となる価値観を定め、組織内で共有します。
- 従業員に伝える: 決定されたMVVを、経営陣が従業員にコミュニケーションし、組織全体に浸透させるための施策(トレーニング、キャンペーンなど)を実施します。
- メリット
- 方向性が一貫し、明確なリーダーシップが発揮される。
- 迅速に決定でき、リーダーが望む変化や戦略を反映しやすい。
- デメリット
- 従業員の声が反映されにくく、組織全体での共感が得られにくい場合がある。
- 価値観が現場の実情に合わない場合、実際の行動と乖離するリスクがある。
2.ボトムアップアプローチ
ボトムアップアプローチでは、現場の従業員が積極的に参加し、組織のミッション、ビジョン、価値観を策定するプロセスです。現場の視点が反映されるため、組織全体に共感や協力を得やすい特徴があります。
- プロセス
- 現場からの意見収集: 従業員やチームが現場の視点で、組織の目的や方向性についてアイデアを出し合います。ワークショップやアンケート、ディスカッションを通じて意見を集めます。
- コアとなるテーマの抽出: 集めた意見から共通点や重要なテーマを見つけ、それを元にミッションや価値観を作成していきます。
- ビジョンの策定: 現場の声を元に、組織全体が共感できる将来像を描きます。
- 経営層による承認と調整: 従業員から出てきたアイデアやテーマを経営層が確認し、最終的に承認します。必要があれば調整を行います。
- 全体での共有: 完成したMVVを全社員に共有し、さらなる意見交換やフィードバックを通じて継続的に磨き上げていきます。
- メリット
- 現場の従業員の視点が反映され、共感や一体感が生まれやすい。
- 実際の業務に即した価値観が形成され、実行可能性が高まる。
- デメリット
- 意見が多様化し、方向性の統一が難しくなる可能性がある。
- 時間とリソースがかかるため、決定に時間がかかることがある。
3.ハイブリッドアプローチ
トップダウンとボトムアップの両方のアプローチを組み合わせることも可能です。両者を組み合わせることでメリットの増幅やデメリットのカバーが見込まれます。経営層が大枠の方向性を示しつつ、現場からの意見やフィードバックを取り入れながら具体的なミッション、ビジョン、価値観を策定することで、効率と共感を両立させることができます。
- メリット
- 経営のビジョンと現場の現実がバランスよく反映される。
- 上下のコミュニケーションが活発になり、組織全体での共有感が生まれやすい。
MVVの策定においては、組織の規模や文化、リーダーシップのスタイルに応じてアプローチを選択することが重要です。
5.レベルゼロのブランディング
言語化だけで終わらない、実際の「行動」を生み出すブランディング
レベルゼロでは、MVV制定からその先までご一緒に伴走いたしています。顧客との信頼関係の構築・差別化の要因の明確化・持続可能な成長基盤の構築など多くのメリットがあるMVVやパーパスの設定を行っています。
会社内や社会の課題をご一緒に分析し、会社の強みを明確に。社内外のステークホルダーを動かすための明確な指針を作り、MVV制定につなげます。既存事業に捉われない自社の社会的大義を設定し、価値観に共鳴する協力者や自社の社員をを動かす宣言文としてパーパスを設定します。
〈 レベルゼロの企業ブランディングとは?〉
https://levelzero.co.jp/service/corporate-branding/